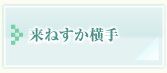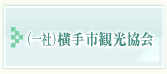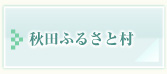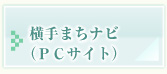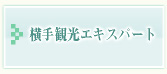たいまつ焼き
たいまつやき













江戸時代から300年以上続いている小正月行事で、五穀豊穣と無病息災を祈るものです。以前は、旧暦の1月15日行われていました。
上醍醐の太刀金地区(現在の醍醐小学校に近い場所で、後に辰金の呼ばれました)には刀鍛冶が、金矢地区
(現在の金屋地区)には弓矢職人がおり、同じ火の神様を奉り参拝しあったのが始まりと言われています。
大たいまつの形は、上醍醐では燈明の芯を表すように細長く、金屋のそれは灯明の台を現すのでずんぐりと作ら
れているところから「うす」と呼ばれています。それぞれ田んぼの中に5本のたいまつをお互いが向き合うように建て燃やします。
この行事はいわゆる「どんど焼き」とは異なるもので、お札や門松などは燃やしません。また男性だけが参加でき、女性はたいまつは勿論、造るわらにも触れてはならないとされ、焼き場所にも行けない事になっています。各家々では、男性の人数だけたいまつを作り、また締める縄の数は奇数とされています。

日 時
1月15日 18:00頃~
会 場
平鹿町醍醐上醍醐地区・金屋地区
所在地
横手市平鹿町醍醐上醍醐地区・金屋地区
[googlemap lat=’39.254405′ lng=’140.524213′ width=’560px’ height=’460px’ zoom=’14’ type=’G_NORMAL_MAP’]たいまつ焼き[/googlemap]
問合せ先
平鹿町観光協会 TEL 0182-24-1118